2007年12月27日掲載
第10回 FTTH型CATVの開発 後編
■業界団体、行政との折衝
CATV関係の主な業界団体に「CATV連盟」と「CATV技術協会」があります。連盟は主に事業者の代表から構成され、CATV事業の発展を促進することを目的に活動しています。技術協会は最新技術の検証や技術基準案の作成を行っています。両者とも総務省と密な連携を保ちながら業界、地域発展のために努力しています。
われわれが進めていたFTTH型CATVの計画が徐々に明らかになってゆくに従って業界団体、特に連盟から厳しい意見が出されるようになりました。彼らの主張は「通信事業者から丸ごと回線を借りてCATVを運営することを認めると、通信事業者に対しCATV事業を認めてしまうことになりかねない」というものでした。つまりCATV事業者の商売が通信事業者に食われるという論理です。これに対し我々の主張は「光ファイバーは同軸に比べメリットが多いので、将来同軸/HFCのネットワークは光に取って代わるであろう。CATV事業者もFTTHを導入することになると思われるが、当面は技術的に優位な通信事業者のFTTHを活用することも一案であろう。今後CATV事業者は設備産業型発想を転換し、コンテンツやサービスを充実し収入の中心にしてゆくべきではないか。そのためにはインフラはその時その時に最適なものを活用してゆくのも手ではないか」でした。
両者の意見は対立しなかなか妥協することはありませんでした。その内連盟を中心に反対勢力が形成され郵政省に対し認可取り下げを要求するようになり我々は厳しい状況に立たされることになりました。
当時郵政省(現総務省)ではCATVは放送行政局の有線テレビジョン放送課が担当していました。まず計画の見通しがついた段階で技術審査を受け、既に認可を得ている従来のHFC方式からFTTH型へ事業認可を切り替える必要がありました。
わが国ではケーブルテレビ事業は有線テレビジョン放送法(有テレ法)、有線電気通信法に従う必要があります。有テレ法は有線テレビジョン放送の施設の許可と業務の届出等の規律が定められています。つまり規模が大きくなると社会性が重視され、テレビ放送の品質を維持できるだけの施設になっているか、滞りなく放送業務が遂行できる会社になっているかなどを事前に審査されるわけです。施設の審査にはあらかじめ専門家によって作成された技術基準が適用されます。今回のFTTH型CATVは施設のほとんどを通信事業者から提供してもらうわけで、従来の自前設備の技術基準がほとんど通用しませんでした。ONU(Optical Network Unit)からの映像出力信号とCATVセンターから通信事業者の局への映像入力信号だけが基準審査の対象になることがわかりました。
後者はCATV事業者が確約することとし前者は通信事業者に確約してもらう必要がありました。つまりFTTHに関わる設備をCATV事業者は提供を受けるわけで、有テレ法ではその設備の内容を技術審査対象にせず通信事業者の責任とすることとなりました。ただしその系を介し結果として得られるONUからの映像出力信号を唯一技術基準の対象とすることになりました。結局NTTはこの部分の技術基準を満たすことを確約したので、審査は無事通過しました。
技術審査が終了した段階で正式に変更申請を作成し提出しましたが、周囲に反対意見があったことなどからなかなか認可が下りず時間が経ってしまいました。
| << | 1 | 3 |
|---|
(コラム記事/ (株)アイ・ビー・イー 坂井 裕)


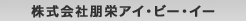
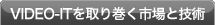
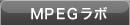
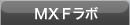


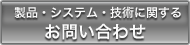
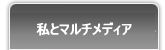
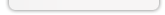
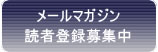
 プライバシーポリシー
プライバシーポリシー