2005�N2�����f��
��25��@���掿��Njy���Đi������ŐVMPEG-2�G���R�[�_�`�b�v
DVD/HDD���R�[�_��PC�ł̃e���r�^�悪��ʉ����Ă����B���v�̊g��ɍ��킹��MPEG-2�G���R�[�_LSI�͐i�����A�g�V����h���}������B����́A��r�I�ŋߓo�ꂵ���V����MPEG-2�G���R�[�_�`�b�v�ɏœ_�����킹�A��\�I�Ȑ��i�Ƃ����̋Z�p�g�����h���T������B
�g�����h��DVD/HDD���R�[�_��AV�p�\�R���B����PC�̐��E�ł́ATV�L���v�`���[�{�[�h���l�C�ł���B�����������i�̒��j���uMPEG-2�G���R�[�_�`�b�v�v���B���v�̍��܂�ɉ�����悤�ɁA�@�\�A���\�̖ʂŐi���𑱂��Ă���B
����́A�ŐVMPEG-2�G���R�[�_LSI(��K�͏W�ω�H)�ɒ��ڂ���B�傫�ȗ���͓������A���^�����BMPEG-2�K�i�����肳�ꂽ�̂�1996�N�ŁA������MPEG-2�G���R�[�_�̓r�f�I�̃G���R�[�h(���k)�@�\�����ő�^(ATX�}�U�[�{�[�h���傫�����炢)�̊��K�v�Ƃ��Ă����B���ꂪ���X�ɏW�ς��i��Ń`�b�v��������A����܂ł̕����̃`�b�v�Œ��Ă����@�\������1�`�b�v�������悤�ɂȂ����B���i�͐̂́u���S����1�v�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B
����Ƀ`�b�v�̏��^�����A�@��̏��^���ɍv�����Ă���B1�`�b�v�ɐ��荞�܂��@�\�͂ǂ�ǂ����A���̍���̎�̑I���@�\�ɂ���āA�`�b�v�̐��i�����܂��Ă���BTV�L���v�`���[�{�[�h�̏ꍇ�́A�ǂ̃`�b�v���g���Ă���̂��̏����{�[�h�x���_�[�����Ă��邱�Ƃ������BMPEG-2�G���R�[�_�`�b�v�̒��g�ɂ��A����ڂ������Ă݂ė~�����B
�ŋ߂�MPEG-2�G���R�[�_�`�b�v4��ނ��r���Ă݂悤�B�\1�ɂ́ANEC�́u��PD61153/61154�v�AConexant System�́uCX23415�v�AViXS System�́uXCODE II�v�A�����d��Y�Ƃ́uMN85572�v�̋@�\�������B
MPEG�K�i�̃r�f�I���k�́A�G���R�[�h�̎�@�ɂ��Ă͋K�肵�Ă��Ȃ��B���̂��߁A�G���R�[�_�ɂ��A�G���R�[�h��@���قȂ�B���R�A�掿���l�X���B��ʓI�ɂ́A�V����MPEG-2�G���R�[�_�`�b�v�͉掿���悢�B������g�����オ���ĕ��G�ȏ������ł���悤�ɂȂ�����A���k�A���S���Y�����i�������肵�Ă��邩�炾�B
�}1�ŕ�����悤�ɁA�ŋ߂�MEPG-2�G���R�[�_�`�b�v�́AMPEG�r�f�I�̃G���R�[�_�����łȂ��AMPEG�I�[�f�B�I�G���R�[�_��A�r�f�I�ƃI�[�f�B�I����̉�����MPEG���d���@�\��1�`�b�v�ɐ��荞��ł�����̂�����B�]���́A�I�[�f�B�I�͕ʃ`�b�v�A���d���̓z�X�gCPU�ōs�����Ƃ����������B

��3����Y/C������H�Ȃlj掿�����P����@�\�𓋍�
�掿�����P���邽�߂ɓ��͉�H�ɂ��H�v���Â炵�Ă���B�m�C�Y������������m�C�Y�t�B���^��A3����Y/C������H�ȂǁA�]���͕�LSI�ō\�����Ă����@�\��1�`�b�v�ɓ����Ă��Ă���̂ł���B3����Y/C������H�́A�P�x�M���ƐF���M��������ۂɕ����̃t���[�����r���āA�Ȗ͗l�̊Ԃ����F�Ɍ�����u�N���X�J���[�v��A�֊s�����ɍ����_���ł�u�h�b�g�W�Q�v�������������H���B
NEC�̃�PD61153/61154�́A��]�̂��铯�Ђ�3����Y/C������H��1�`�b�v�Ɏ��߂Ă���B�܂��ATBC(�^�C���x�[�X�R���N�^�[)�Ƃ����r�f�I�M���̎��Ԏ��̘c�݂������H�����ڂ��A��荂���掿��Njy�B���ɏ��Ȃ����i�_����MPEG-2�̃G���R�[�h���s����B
�\�j�[�̒����@�\AV�p�\�R���uVAIO Type X�v�ɓ��ڂ���ėL���ɂȂ���ViXS��XCODE II��3����Y/C������H�������Ă���B����LSI�ɂ́A����Ɂu�g�����X�R�[�h�v�@�\�����ڂ���Ă���B�g�����X�R�[�h�́AMPEG-2�f�[�^�����Ⴂ�r�b�g���[�g�ɕϊ�����ۂɁA�f���������e��������A�`�b�v�����ōăG���R�[�h����@�\���B�f�W�^����������M���Ę^�悷��ꍇ�ȂǂɁA�g�����X�R�[�h�@�\������ƁA��荂���掿�Ř^��ł���\��������B
Conexant��CX23415�����@�\���B3����Y/C������H�͂Ȃ����A�m�C�Y�t�B���^�𓋍ځBMPEG-2�̃G���R�[�_�����łȂ��f�R�[�_��1�`�b�v�ɏW�ς��A����ɉf���Đ���ʂɃ��j���[��������d�˂ĕ\�����邽�߂�OSD(�I���X�N���[���f�B�X�v���C)�@�\�܂Ŏ����Ă���B�}�ɂ͕`���Ă��Ȃ����A����LSI�ɂ��g�����X�R�[�h�@�\������AMPEG-2�f�[�^���Đ����Ȃ���A�ʂ̃r�b�g���[�g�̃f�[�^������B�f�W�^�������̃`���[�i�[�A���R�[�_�ȂǂŊ������Ȑ��i���B
�����d���MN85572�́A�l�C���iMN85560�̌�p�@��ƍl���Ă悢�B������グ�����̐��i�Ɣ�ׂ�Ƌ@�\�̑����ł͌���肷�邪�A�掿�����コ������̓t�B���^�������B

���܂��܂��悪����掿���P�̃e�N�m���W�[
3����Y/C������m�C�Y�t�B���^�́A�掿�����P���邽�߂́A���͂�g�펯�I�h�ȉ�H�����A�掿���P�̂��߂̎�@�͂܂��܂��J�����i�߂��Ă���B���̂��������ȒP�ɉ�����悤�B
�uAFF(�K���^�t�B�[���h�^�t���[��)�v�́A�e���r�M���̂悤�ȃC���^���[�X�f�����G���R�[�h����ہA�}�N���u���b�N�ƌĂ�鐳���`�̃G���R�[�h�P�ʂ��ƂɁA�t���[���\���ŃG���R�[�h���邩�A�t�B�[���h�\���ŃG���R�[�h���邩�f������̂��B�ǂ���ŃG���R�[�h���������掿���オ�邩���u���ɔ��f���鏈�����K�v�ɂȂ�B
�u�t�e���V�l�v�́A30�t���[��/�b�̃r�f�I�M����24�t���[��/�b�ɕϊ����鏈���B�f��͖��b24�t���[���ŁA�t�B�������r�f�I�M���ɕϊ�����ۂɁA���b30�t���[���ƂȂ�悤�ɁA�����t���[�����_�u�点���肷��̂��u�e���V�l�v���B�t�e���V�l�́A�]���ȃt���[������菜�����ƂŁA�掿���啝�Ɍ��シ��B�u�V�[���`�F���W���o�v�́A�V�[��(���)���ς�������ǂ��������o���鏈�����BMPEG�ł́A�t���[���Ԃ̍��������o���A���ʕ����͏ȗ����邱�Ƃň��k�����グ�Ă���B���̕��@�ł́A�����V�[�����������͌������ǂ����A�V�[���`�F���W������ƁA�������g��Ȃ������掿�������Ȃ�ꍇ������B
| ���[�J�[�� | NEC | Conexant Systems | ViXS System | �����d��Y�� |
|---|---|---|---|---|
| ���i�� | ��PD61153/61154 | CX23415 | XCODE�U | MN85572 |
| ���͏��� | 3����Y/C�����A �^�C���x�[�X�R���N�^�[�A �m�C�Y�t�B���^ |
�m�C�Y�t�B���^ | 3����/C�����A �m�C�Y�t�B���^ |
�t�B���^ �i���Ԏ��A�����A�����j |
| ���[�g���� | CBR/VBR | CBR/VBR | CBR/VBR | CBR/VBR |
| GOP�\�� | �ρA�V�[�`�F���W���o | �ρA�V�[�`�F���W���o | �ρA�V�[�`�F���W���o | �ρA�V�[�`�F���W���o |
| ���̑��̃r�f�I | �t�e���V�l | �摜�������o | �t�e���V�l�AAFF | �t�e���V�l�AAFF |
| ���������͈� | �ő�}128 | 4��f���x�ő�}60�` 1��f���x�ő�}15 |
1/2��f���x�}300 | 1/2��f���x�ő�}326 |
| VBI���o | �� | �� | �� | |
| �I�[�f�B�I�G���R�[�h | Layer2 | Layer2�ADolby | Layer2�ADolby�AAAC�AMP3 | Layer2 |
| �g�����X�R�[�h | �� | �� | ||
| ���̑� | MPEG-4 Video ASP �G���R�[�h�ɂ��Ή� |
��CBR�F�Œ�r�b�g���[�g�AVBR�F�σr�b�g���[�g�AGOP�FI�s�N�`���[����n�܂��A�̃t���[���AAFF�F�K���^�t�B�[���h/�t���[���AVBI�F�����A����������
�\1 �e���[�J�[�̍ŋ߂�MPEG-2�G���R�[�_�`�b�v�̋@�\�̓���(�ꕔ����j�B3����Y/C�����Ȃǂ̕t���@�\�͊O�t��H�Ŏ���������@������̂ŁA1�`�b�v�ɂ�����W�ς��Ă��Ȃ����Ƃ��@�\�s���Ɍ��т��킯�ł͂Ȃ��B

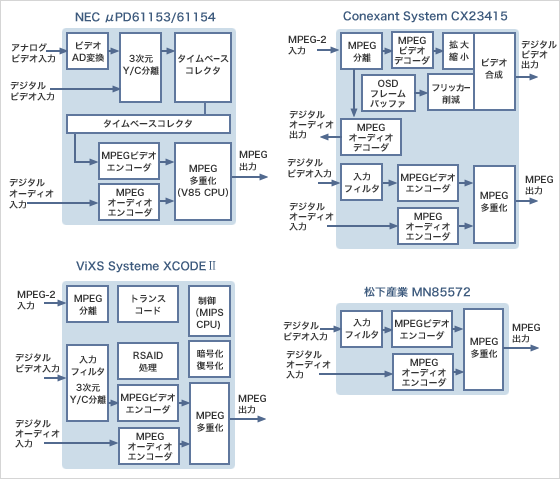
��OSD�F�I���X�N���[���f�B�X�v���C�i������j���[�Ȃǂ̑��d�\���j
�}1 ���[�J�[4�Ђ�MPEG-2�G���R�[�_�`�b�v�̊T�v(�ꕔ����) MPEG�r�f�I�G���R�[�_�ɉ����āA�ŋ߂ł�MPEG�I�[�f�B�I�G���R�[�_�AMPEG�̑��d���Ȃǂ̕t����H��1��LSI�ɏW�ς��Ă���B
(��/ �|�� ���A(��)���h�A�C�E�r�[�E�C�[) ���ҏW�̊W��A�G���f�ړ��e�Ə����قȂ��������܂��B


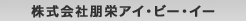
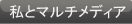
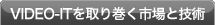
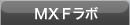

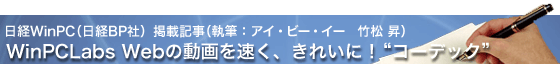
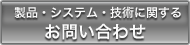
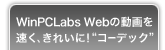
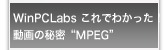
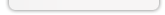
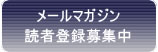
 �v���C�o�V�[�|���V�[
�v���C�o�V�[�|���V�[