2008年12月12日掲載
第32回 BMLの仕様から見るデータ放送の今後<その3>
データ放送を取り巻く環境の変化
執筆:クワトロメディア株式会社 長谷川修平
執筆者プロフィール
システムの視点からは、視聴から即座に購買に結び付けられる理想的な双方向システムに見えます。デジタル放送が開始されたころに提供されていた通販システムも概要としてはこの様なものでした。
ですが残念ながら、現実にはこういったサービスが普及しているとは言えない状況にあります。デジタル放送が開始されて間もない頃は、主に据え置き型テレビで視聴されることが想定されました。当然、「テレビに通信回線が接続されているか?」という根本的な問題が挙がります。
コンテンツが通信との連携を考慮しても、そもそも受信機が通信接続されていなければ、双方向という言葉は成立しません。「通信との連携」を考慮した機能も、肝心の回線が接続されていなければその真価は発揮しようもありませんでした。
最近では、当初の問題であった「通信回線の接続」が急速に解消されつつあります。据え置き型のテレビに関していえば、アクトビラのような通信回線経由でオン・デマンドを提供するサービスの拡充も要因の一つです。
NHKによる映像コンテンツの提供は大きな話題と言えるでしょう。また、受信機メーカー、放送事業者、通信事業者が参加するIPTVフォーラムによる標準規格の策定など、普及に向けた取り組みが成されていることにも大きな期待が寄せられています。
このように、視聴者にとって受信機に通信回線を接続するメリットが増えれば、環境は大きく変わって行くということです。
一方、ワンセグ放送は主に携帯電話での視聴を想定しており、大半が通信接続できる状態にあります。ワンセグの視聴に対応した携帯電話の出荷台数は4000万台を超えたと言われています。そして、08年4月にサイマル規制が解除され、放送局ではワンセグの独自放送を実施する動きが見られます。
また、VHFの空き周波数で提供される予定のマルチメディア放送も実用化に向けた動きが活発化しており、近い将来データ放送を用いた新しいサービスが出現するかも知れません。
このように提供されるサービス、コンテンツ、受信機の変化に伴い、放送と通信の関係が深まりつつあり、BMLが備える双方向の通信機能が有効に活用される環境が整い始めているとも考えられます。そして、新しい放送においてデータ放送の記述言語としてBMLが採用されている点は開発者としては嬉しい限りです。
2 |
BMLについてさらに詳しく知りたいと思って頂けた方は、下記のページで「BMLスクール」の開催をご案内していますので、是非ご覧下さい!(2008年12月現在)
http://www.qmedia.co.jp/bml/index.html
(コラム記事/クワトロ・メディア 株式会社 長谷川修平)


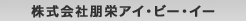
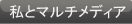
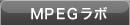
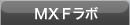


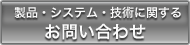
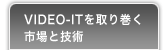
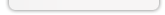
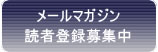
 プライバシーポリシー
プライバシーポリシー