2008年3月13日掲載
第28回 <屋外広告物としてのデジタル・サイネージのこれから>
chapter 04 デジタル・サイネージのコンテンツ
コラム執筆:株式会社シブヤテレビジョン 技術部
シブヤテレビジョン技術部について
■飽和するコンテンツ制作業務
デジタル・サイネージで使用するコンテンツはテレビCMのような既存のものもありますが、ほとんどはその都度作成していかなければいけません。そうなると実務を行なう「制作」の人足が問題になります。近年PCの普及により、映像や音楽の制作ははるかに簡単になりました。しかし、それはあくまでオペレーション的なことだけであり、クオリティの高いものを作ることには結びつきません。ソフトウェアも便利なものが多数販売されていますが、結局は「人がつくるものであり、そこには「センス」というものを無視することはできません。制作会社(もしくは個人)にしてみれば、デジタル・サイネージをはじめとするメディアの拡大によって、仕事が増えることはよいことです。しかし、その反面、仕事量が過剰になってしまうと単価が下がり、一つ一つのクオリティを下げてしまう、もしくは同じような型にはめるだけになってしまうことも否めません。そのような悪循環があまりに長く続いてしまうと、せっかくメディアの拡大ができても「箱だけ立派で中身はからっぽ」状態になってしまいます。
| 写真2:デジタル・サイネージの例、自動販売機のモニター。1台だけでは効果が少ない。 |
デジタル・サイネージはウェブサイトのように、インタラクティブな要素を持っています。そのため、各媒体機器における動作条件も考慮したうえでコンテンツを制作し、機械的な動作確認なども行なう必要があります。従来の広告以上に行なわなければいけないことが増えてきているため、コンテンツの制作には「発注者」と「制作者」の間でのコンセンサスや様々な予備知識がとても重要になります。
■デジタルサイネージを広告媒体として普及させるには
今まで4回にわたってデジタル・サイネージを広告として活用するための問題点を挙げてきました。定義の決まっていないこのメディアを普及させるには、「機械メーカー」「媒体主」「広告主」「コンテンツ制作者」の間で秩序をもち、なおかつ今までにない新しい発想の転換をしていかなければいけません。
テクノロジーの発展により、様々な広告媒体が生まれてきています。その中でもこの「デジタル・サイネージ」は、公共空間におけるとても自由な、そしてとても制約のある媒体です。
各関係者が利己的な考えをしてしまうと、せっかくの無限の可能性をつぶしてしまうことになります。「デジタル・サイネージ」に関わっている、もしくはこれから関わっていこうと思っている方々には、ぜひとも、それに関わる自分以外の人々の立場をくみとり、充分な予備知識と新しい発想をもって臨んでいただければと思います。
<参考URL>
・デジタルサイネージコンソーシアム
http://www.digital-signage.jp/
・クリック詐欺
http://japan.zdnet.com/security/story/0,3800079245,20354753,00.htm
・ラッピングパス
http://ja.wikipedia.org/wiki/ラッピング車両
2
|
(コラム記事/ シブヤテレビジョン 技術部)


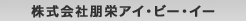
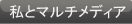
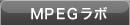
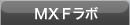


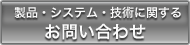
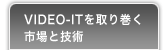
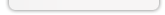
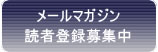
 プライバシーポリシー
プライバシーポリシー