2006年8月24日掲載
第1回 MXFとは何か
業務用映像ファイルフォーマットとして開発されたMXF(Material eXchange Format)について、その概要と位置づけについて述べる。ここ数年、放送局の方々にMXFについて説明し、議論してきた。また、検証のためのシステムをいくつか開発してきた。これらの経験を踏まえ、数回に分けてMXFについて整理したい。

1.MXF規格とは
2.MXF規格の背景
3.MXF規格で規定されている内容
4.MXF規格の映像・音声の形式
5.標準メタデータDMS-1
6.標準以外のメタデータ
7.SMPTEのMXF規格一覧

MXF(Material eXchange Format)は、映像の規格策定団体であるSMPTE*1で規格化された業務用映像ファイルフォーマットだ。映像をファイル化する際の「入れ物」、つまり乱暴に言うとVTRテープケースやVTRカセットに相当するものと捉えることができる。この「入れ物」であるMXFには、映像や音声をデータ化して格納できるほか、さまざまなメタデータや関連データを格納することができる。また、映像をファイルで運用する場合に必要となるさまざまな機能を持つ。MXFは、将来拡張可能な非常に自由度の高い規格として考えられている反面、規格のどの部分を使うかで機能や互換性が違ってくる。
※1 SMPTE(Society of Motion Picture and Television Engineers、米国映画テレビ技術者協会)、映画やテレビ放送に関する標準技術規格を策定している団体。たとえば、D2 VTRのD2はSMPTE 245M〜248Mの規格となっている。

コンピュータやネットワークなどIT技術の高性能化に伴い、映像をファイルとして取り扱うことができるようになってきた。ノンリニア編集機やビデオサーバなど、「テープレス」のビデオシステムがさまざまな用途で使われるようになってきた。しかし、これらの機器は多くの場合独立しており、LANやWANで映像データをやりとりするなどIT技術を使うメリットをすべて享受できていない。以前のワープロ専用機と同じ状況だ。映像をファイル化し、LANやWANでやりとりすることで、従来のVTRテープとは違う運用が可能となるが、ファイル化のメリットを引き出すためには、従来の映像ファイルフォーマットでは不足する面が多かった。メーカー間、機器間の互換性問題がまず存在する。業務用途で使用する場合、単に映像・音声を格納するだけでなくタイムコードやメタデータを格納する機能が必要だ。また、プレイリストなどを格納できるなど、さまざまな付加情報を規定し格納する機能があると良い。
VTRテープを使った従来の運用では、テープに必ずテープ記録表を添付する。テープ記録表には、タイトルやタイムコード情報、音声チャンネルに関する情報、制作に使った機器や担当者名が書かれる。従来の映像ファイルフォーマットだと、テープ記録表に相当するメタデータを埋め込む機能は標準化されていなかった。ユーザ独自に埋め込むことは、従来のフォーマットでも可能だが、これでは互換性がとれないためシステム費用や運用費用が安くならない。MXFを使うと、この点が解決する。さらに複雑なメタデータを添付することも可能だ。
MXFは、放送関係者とビデオ機器会社が集まって設立された業界団体の一つPro-MPEG Forumと、SMPTE+EBUの共同プロジェクトが連携して策定された。1999年に開始されたMXFプロジェクトは、EBUとSMPTEが1996年から進めてきたファイルによる番組交換のための標準化プロジェクトと合流し、標準化作業の後にSMPTEの標準規格となった。MXFは、ノンリニア編集システム間での映像・音声・編集情報の互換性をとるために開発されたAAF(Advanced Authoring Format)と並行して開発された。MXFとAAFは、メタデータなどの互換をとりやすくするため、基本データ構造を同じにするなど工夫されている。
MXF策定にあたり、以下の要求条件(*2)がまとめられた。
- 番組の映像・音声と同様に、番組に関するメタデータやさまざまなデータを持つことができる。
- ファイル伝送が完了する前に、受け取り側で次の処理をスタートできる。
- ファイル伝送時にデータの一部が欠落しても、残りの部分を再生できる機能を持つ。
- ファイルフォーマットはオープンな標準で、かつ、圧縮方式から独立している。
- 番組全体もしくは番組の一部をやりとりすることができる。
- リアルタイムで処理できる簡潔さを持つ。
- 拡張可能でOSや伝送方式、格納されるメディアから独立している。
これらの要求条件を満たす規格として、MXFは設計されている。MXFは万能ではないものの、さまざまな点を考慮して設計されており、業務用映像ファイルフォーマットの決定版といって良い。ファイルとして映像を利用するシステムを構築していく上で、MXFを利用しない手はない。
※2 Nick Wells編、The MXF Book (Focal Press 2006年) 、SMPTE EG-41による。

MXFでは、自由度と互換性と相反する機能を非常に巧妙にまとめている。まず、映像や音声については、さまざまな圧縮方式を許容している。この中には非圧縮の映像・音声も含まれる。これは現実に、さまざまな圧縮方式が実用されていることと、今後も改良・開発が続くため固定できないという背景がある。映像・音声の圧縮形式が異なると、この部分では互換性がとれない。ただし、このような場合でも、メタデータの形式が共通であれば、メタデータについては互換性がとれる。例えば、再生時間や、タイトル、内容説明、権利情報などのメタデータが共通であれば、映像・音声の形式が違っていても、コンテンツ管理上は一元的に処理でき、処理の自動化も可能となる。
実際は、メタデータを統一することも難しい。用途・目的によってさまざまなメタデータが存在するためだ。ただ、何らか統一しないと共通性・互換性がとれないため、MXFではメタデータについて次のように整理された。まず、コンテンツの技術的な要件についてのメタデータ、つまり圧縮方式、解像度や再生時間などについては、すべてのMXFに共通の構造系メタデータ(Structural Metadata)として規定された。一方、コンテンツの内容、つまりタイトルや内容説明、権利情報などは記述系メタデータ(Descriptive Metadata)として、任意のメタデータを許容することになった。また、記述系メタデータについても、共通のメタデータDMS-1(Descriptive Metadata Scheme)が規定された。つまり、DMS-1互換のメタデータを格納しておけば、メタデータについてはかなり互換性がとれる。

前述のように、MXFは映像・音声の圧縮方式には依存しない規格だが、圧縮方式毎に具体的な格納方法についての規定が規格化されている。これまでに、非圧縮ビデオ、DV(DV、DVCAM、DVCPRO25/50/HD)、D-10(IMX)、D-11(HDCAM)、MPEG-1/2(Long GOP、I-only、Audio、TS、PS)、JPEG-2000、非圧縮音声(AES3、BWF)が規定されている。(7. SMPTEのMXF規格一覧を参照)これは、今後順に拡張され、新しい圧縮方式に対応していくと考えられる。MPEG-2の場合、MPEG-2 Videoを単体(エレメンタリー・ストリーム)で格納する方法と、MPEG-2 TSやMPEG-2 PS形式として格納する方法の両方が規定されている。後者の方法を使うと、MPEG-2 TSデータに含まれる、データ放送用データなどもまとめて格納することができる。
映像・音声の他、タイムコード、VBI信号、SDIのアンシラリデータなどを格納することもできる。タイムコードについては規格として策定済だが、VBI信号やSDIのアンシラリデータについては、規格策定が進行中だ。

標準メタデータスキームDMS-1は、MXFの記述系メタデータの標準として策定された。他のメジャーなメタデータ標準である、AAFとの連携はもちろん、MPEG-7、TV Anytime、P/Metaとの連携も考慮して策定された。DMS-1は、以下の3つのフレームワークで構成され、各フレームワークはさまざまなメタデータ項目を持つ。
- Production(作品につけるメタデータ)
- Clip(素材につけるメタデータ)
- Scene(特定の場所につけるメタデータ)
DMS-1は、さまざまなメタデータの最大公約数として策定されている。項目名は決まっているが、その項目にどのような内容を書くかについては規定がない、ゆるやかな規定である。文字数の規定もない。実際の運用では、運用ルールを決めないと、あいまいになってしまう。例えば「タイトル」一つをとっても、さまざまな解釈がある。連続ドラマの場合、シリーズ名称なのか、その回の内容なのか、など。DMS-1では、権利情報も記述可能だ。例えば、Participants(関係者)、Contact List(連絡先)、Contract(契約情報)といった中項目がある。
DMS-1のデータは、ファイル上ではバイナリデータとして格納される。MXFを取り扱うシステムやソフトがメタデータを取り出したり読み込んだりする場合は、XML表現とすることが多い。なお、DMS-1に不足するメタデータ項目はユーザサイドで拡張可能だ。ただし、独自に拡張すると拡張部分の互換性がなくなってしまう。DMS-1のみで使う場合、拡張する場合、のいずれにしてもMXF運用のためのメタデータの業界標準を用途毎に設定する必要がある。例えば、報道素材用など。

DMS-1と全く違うデータ体系の場合や、DMS-1とは別にオリジナルのメタデータを格納したい場合、別のメタデータそのものを格納することもできる。規格外のメタデータはダーク・メタデータと呼ばれるが、このメタデータを知らないシステムは単に読み飛ばす。
DMS-1との共通項目はDMS-1、その他はオリジナルのメタデータ、と両方のメタデータをあわせて格納しておくと、オリジナルメタデータを知らない他のシステムはDMS-1と共通のメタデータ項目をDMS-1から読むことができ、最低限の互換性を保つことができる。

| SMPTE 377M-2004 | MXF本体 |
| SMPTE 378M-2004 | オペレーショナルパタンOP1a(単一項目、単一コンテンツ) |
| SMPTE 379M-2004 | MXF汎用コンテナ(GC) |
| SMPTE 380M-2004 | メタデータDMS-1(Descriptive Metadata Scheme-1) |
| SMPTE 381M-2005 | GCにMPEGを格納 |
| SMPTE 382M | GCに非圧縮音声(AES3、BWF)を格納 |
| SMPTE 383M-2004 | GCにDV-DIFを格納 |
| SMPTE 384M-2005 | GCに非圧縮映像を格納 |
| SMPTE 385M-2004 | GCにSDTI-CPデータを格納 |
| SMPTE 386M-2004 | GCにD10(IMX)を格納 |
| SMPTE 387M-2004 | GCにD11(HDCAM)を格納 |
| SMPTE 388M-2004 | GCにA-lawオーディオを格納 |
| SMPTE 389M-2005 | 逆再生用データ格納 |
| SMPTE 390M-2004 | オペレーショナルパタンOP-Atom |
| SMPTE 391M-2004 | オペレーショナルパタンOP1b(単一項目、集合コンテンツ) |
| SMPTE 392M-2004 | オペレーショナルパタンOP2a(プレイリスト、単一コンテンツ) |
| SMPTE 393M-2004 | オペレーショナルパタンOP2b(プレイリスト、集合コンテンツ) |
| SMPTE 407M-2006 | オペレーショナルパタンOP3a,OP3b |
| SMPTE 408M-2006 | オペレーショナルパタンOP1c, 2c and 3c |
| SMPTE 422M | GCにJPEG2000を格納 |
※SMPTE 382M、SMPTE 422Mは、規格としては審議中。
(文/ 竹松 昇、(株)朋栄アイ・ビー・イー)

 このテーマを活用する このテーマを活用する |
 |
最新技術を利用したソリューション |
 |
映像の再利用とアーカイブ | |
 このテーマを製品化すると このテーマを製品化すると |
 |
MXFレコーダ MXF-300so |
 |
MXF::SDK | |
 |
MXFComponetSuite | |
 |
theScribe LITE | |
 |
theScribe PRO |


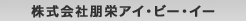
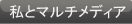
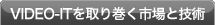
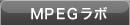


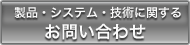
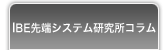
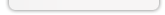
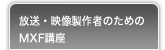
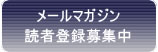
 プライバシーポリシー
プライバシーポリシー